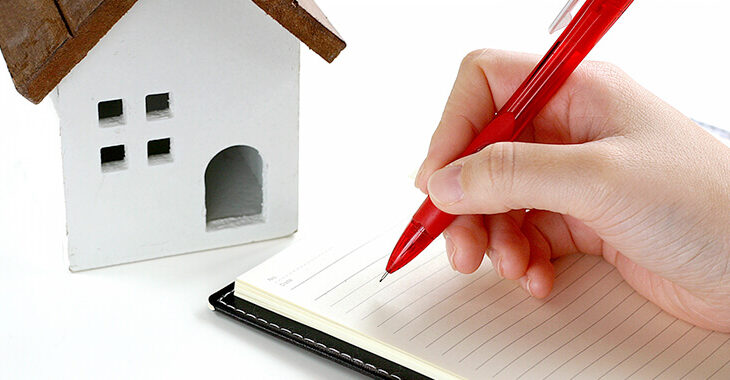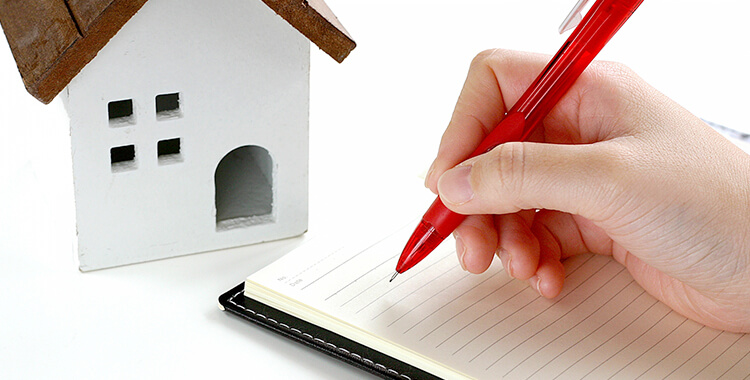
離職など失業した方などを対象に家賃補助が受けられることはご存知でしょうか。
地方自治体や世帯人数によって支給額は異なりますが、一定の条件を満たすことができれば支給してもうらことできるので、上手に活用し転職活動に活かしましょう。
関連記事:転職時に貯金はどれくらい必要?転職活動に必要な費用を解説!
住宅確保給付金とは?
生計維持者が離職・廃業後から2年以内である場合や個人の責任・都合によらず離職・廃業と同程度まで給与が減少している場合において、一定の要件を満たすことができれば地方自治体から家賃額を補助してもらうことができる制度です。
支給期間について
原則3ヶ月間(延長は2回まで最大9ヶ月間)
支給額について
支給額はお住まいの市区町村や世帯人数によって異なります。
支給上限額の詳細については、お住いの自治体に問い合わせてみましょう。
賃貸物件への家賃補助になるので、共益費・光熱水費・借地代・住宅ローンなどは対象外となります。
東京都特別区の場合、下記の支給上限額になっています。
| 世帯の人数 | 1人 | 2人 | 3人 |
|---|---|---|---|
| 支払い上限額(月額) | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 |
対象要件
住宅確保給付金を受給するには下記の要件を満たす必要があります。
1.A:主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、B:個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
2.直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
3.現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
4.1のAの場合:ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(ハローワークへの求職申込、職業相談を月2回、企業への応募・面接を週1回 )、1のBの場合:誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(家計の改善、職業訓練等)
出典:厚生労働省
申請方法と手順について
住宅確保給付金の申請は、自治体などが運営を行う生活困窮者自立相談支援機関に相談・申請を行います。生活困窮者自立相談支援機関は、全国905箇所の福祉事務所設置自治体で1,317箇所設置されています。
生活困窮者自立相談支援機関を介して自治体に申請する形となります。
自治体によっては、市町村が運営するホームページのフォームから申請を行うことができる自治体もあります。
お近くの相談窓口を調べる際は、下記の厚生労働省の資料をご参照ください。
参考:厚生労働省「自立相談支援機関窓口情報」
必要書類
・申請する本人の収入が確認できる書類(給与明細、年金等の公的給付金の証明書など)
・預貯金額が確認できる書類(申請をする方及び同居されている親族等の金融機関の通帳コピー)
・離職・廃業や就労日数・就労機会の減少が確認できる書類
離職・廃業後2年以内の場合:離職票や離職証明書、廃業届など。
個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合:(例)雇用されている方の場合、勤務日数や勤務時間の減少が確認できるシフト表等。