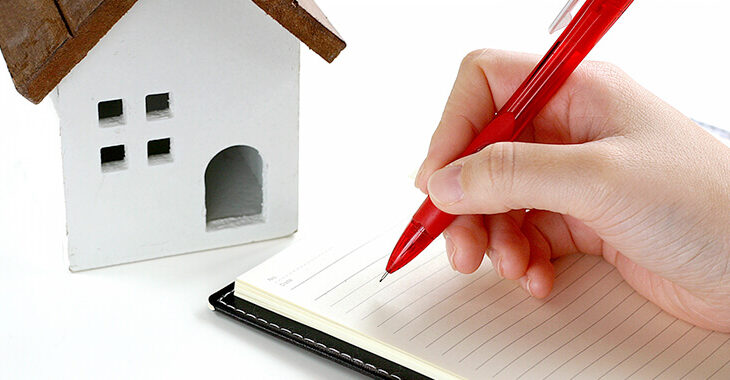「退職届を受理してもらえない」、「なかなか退職させてもらえない」などスムーズに退職できないというケースが増えてきています。
今回は、スムーズに退職を進めることができる対処法をご紹介します。
最短2週間で法律上は退職することができる
法律では会社員など雇用期間の定めがない場合、退職の申し入れから2週間経過すると雇用契約が終了すると規定されています。
つまり労働者には「退職の自由」が保障されており、自由に退職することが可能です。
契約社員や派遣社員など雇用期間に定めがある場合は、契約満了ままた雇用契約後1年以内はやむを得ない事情がない限り退職できません。
また労基法第15条によって、明示された労働条件と事実が異なる場合は労働契約を即時解除が可能です。
ただしお世話になった会社へ迷惑をかけないように、引き継ぎ期間も含めて1~3ヶ月前に退職の意思を伝えて円満退職を目指して進めていきましょう。
期間の定めのない雇用の場合(民法第627条第1項)労働者には「退職の自由」がある。そのため、退職を希望する労働者は自由に退職することができ、退職の意思表示から2週間が経過すると雇用関係が終了(=退職)する。
出典:日本労働組合総連合会
期間の定めのある雇用の場合(民法第628条) 労働者の「退職の自由」そのものが否定されている訳ではないが、労働者からの解約(=退職)の申入れについては「やむを得ない事由があるとき」に制限されている。この場合、退職の理由が「やむを得ない事由」に該当すると判断されるかどうかは個々の事例によるため注意が必要である。なお、1年を超える有期労働契約の場合で、契約の初日から1年を経過した日以降は、いつでも退職することができる(労基法第137条)。
出典:日本労働組合総連合会
関連記事:ホワイト企業の特徴と見分け方を身につけよう
関連記事:退職を伝える「時間・曜日・時期」などのタイミングについて
退職させてもらえない場合の対処法5選!
退職届を受理してもらえない場合
退職届を受理してもらえない場合は、内容証明郵便で郵送すると効果的です。
内容証明郵便とは、「差出人が受取人に対してどのような内容の郵便をいつ郵送したのか」という情報が郵便局に記録されるサービスです。
内容証明郵便を利用することで、会社が退職届を受け取った日にちを証明することができます。
最短で内容証明郵便を会社が受け取った日から2週間後に退職することが可能です。
口頭で退職の意思を伝えることでも問題はないとされていますが、言った言わない問題への発展を事前に防ぐためにも有効的な対処法です。
内容証明郵便の手数は440円、2枚目以降は260円増しで利用することができます。
人手不足などの理由で退職日までの期間が長い場合
人手不足や繁忙期などの理由で退職日を延ばされるケースもよく発生するケースです。
引き継ぎ作業なども大切ですが、退職日も何度も延ばされる可能性もあるのでしっかりと退職の意思を伝えるようにしましょう。
法律では退職の意思を伝えて2週間で退職することは可能なので、引き継ぎなどが完了したら速やかに退職しても問題はありません。
懲戒解雇処分にすると言われた場合
懲戒解雇とは、会社の規約に違反したり、法律違反、経歴詐称、過度なパワハラ・セクハラなどの問題を起こした場合に行われる処分です。
つまり従業員が違反行為を一切行っていないにもかかわらず、会社側は強制的に懲戒解雇処分することはできません。
万が一不当な懲戒解雇処分された場合は、労働基準監督署または弁護士などに相談しましょう。
違約金を請求された場合
会社の就業規則に違約金について記載があり、サインを行ったとしても違約金を支払う必要は全くありません。
賠償予定の禁止(第16条)では「労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。」と定められています。
違約金に関する就業規則を定めることが禁止されているので断固拒否しても大丈夫です。
万が一給料などから強制的に天引きされてしまった場合は、労働基準監督署に一度相談してみましょう。
損害賠償請求を請求された場合
先ほどの違約金と同様に損害賠償を請求する場合も「賠償予定の禁止(第16条)」に当たります。
ただ退職が理由で大きな商談がなくなってしまったり、会社に対して大きな損害を与えてしまった場合は損害賠償を請求される可能性はありますので退職時期には注意しましょう。